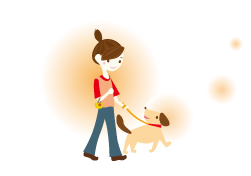本文
ペット飼育に関するQ&A(仮設住宅編)
応急仮設住宅に入居されているペット飼育者の方向けのQ&Aを掲載しています。
ペット飼育に関するQ&A(仮設住宅に入居された方向け)
Q1 これまで外で飼っていたペットを室内で飼うことはできますか?
A1 大型犬なども室内に入れてみましょう。意外とうまくいきます。東北でもかなりのケースで成功しています。
試してみて無理なら、その時方法を考えましょう。
問題を一人で抱え込まず熊本地震ペット救護本部にご相談ください。
Q2 仮設住宅でペットを飼うときに健康面で注意することはありますか?
A2 ペットも慣れない環境で暮らすのですから程度の差こそあれストレスを受けています。
普段からペットをよく観察し異常があるときは動物病院に相談してください。
動物から人に伝染する病気もありますから、かかりつけの動物病院で定期的に健康診断を受けましょう。
Q3 ペットの身元表示は必要ですか?
A3 ペットが逃げ出してしまった場合、仮設住宅など慣れない環境では自力で戻ってくることは困難です。
そのためはぐれてしまったペットが飼い主の元に戻れるよう身元表示をつけましょう。
ペットに迷子札をつけたり、マイクロチップというデータベース化した情報から身元検索できるチップを皮下に埋め込む方法があります。
(マイクロチップの埋め込みは動物病院での施術が必要です。)
*犬の場合、狂犬病予防法という法律で、市町村から交付された鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着しなければならない規定があります。
必ず首輪などに着けましょう。
Q4 仮設住宅で近隣の人に迷惑をかけないか心配です。
A4 仮設住宅ではペットを飼っていない人や動物が苦手な人もいます。このような人たちにも気を配ってペットを飼う必要があります。
ペットに関する苦情で多いのが鳴き声などの騒音とペットの発する臭いです。
ストレスが多いと鳴く傾向が高まりますので散歩を十分に行ったり、触れ合う時間を多くとってストレスを発散させてあげてください。
また臭い対策では、ペットの身体をきれいに保ち、ケージやトイレもこまめに清掃を行いましょう。
Q5 不妊去勢手術はしたほうがよいですか?
A5 発情期には雄雌ともに落ち着きがなくなったり、発情期特有の鳴き声を頻繁に発するなど普段とは全く違う行動をします。
近隣の迷惑になる恐れがあるばかりでなく、異性を求めて逃げ出す事例も増えます。
無事戻ってきたら赤ちゃんが生まれてしまったなどの問題が起きることも。特別な事情がなければ不妊去勢手術を行いましょう。
ペットが年をとってかかる病気(精巣がんや子宮蓄膿症など)の予防にもなります。
Q6 不意な訪問客に犬が飛びかかってしまう恐れがあります。
A6 このような事例があるとお互いに驚いてしまいますね。悪くするとトラブルの原因にもなります。
予防策として、玄関にペットを飼っている旨の張り紙やステッカーを玄関の目立つ所に掲げ、訪問客に注意を促しましょう。
また、犬が飛びかからないように、日頃から「待て」や「伏せ」などの基本的な号令に従うようしつけを行ったり、
室内に柵を設置したりして犬が飛びかからないようにしてください。
万一、飼っている犬が人を咬んでしまったら、保健所に連絡してください。
Q7 犬の散歩時の注意点について教えて下さい。
A7 散歩時は、犬もうれしくて興奮しているので、仮設住宅の敷地内では犬が人を咬んだり、排尿するなどトラブルになる可能性があります。
そのため敷地内では犬を抱きかかえる、引き綱を短く持って犬を制御するなど配慮が必要です。
またビニール袋と水を入れたペットボトルを携帯し、排便はビニール袋に入れて持ち帰り、排尿は水で流すようにしましょう。
草むらなどで遊ばせると,ノミやダニをつけてしまうので動物病院で定期的に薬を処方してもらいましょう。
犬についたノミやダニは、人にもうつるだけでなく、重篤な病気を引き起こす恐れがあります。