本文
清和文楽館

人口4,000人に満たない、清和村。
この村には、江戸時代から受け継がれてきた清和文楽が、今も生きている。この建物は、文楽の上演、及び映像や人形展示等によって文楽を紹介するための施設として建設された。
美しい自然環境と調和するように、ここでは日本古来の木材を生かした伝統建築技術が用いられている。
建築概要
清和村に江戸末期より伝わる文楽を伝承していくための劇場である。
清和村はもとより、文化庁、林野庁より木造の希望があり、在来工法の大型のものを計画した。軒高9m、最高高さ13mという建築基準法の限度一杯につくられる。奈良時代以降、在来工法は木の重なりによってつくられていることを活かしている。全国に今でも、1,000以上ある能の舞台の九州を代表するものとなることを期待している。
観客総数200。

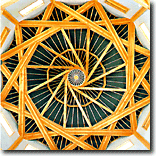
Photo:石丸捷一、KAP事務局
建築データ
| 名称 | 清和文楽館 |
|---|---|
| ふりがな | せいわぶんらくかん |
| 所在地 | 上益城郡山都町大平原口152 (清和文楽館HP)https://seiwabunraku.com/<外部リンク> |
| 主要用途 | 文楽劇場+展示館 |
| 事業主体 | 清和村(現・山都町)) |
| 設計者 | 石井和紘 |
| 施工者 | |
| 建築 | 日動工務店 |
| 電気 | 西邦電気工事、砥用電設 |
| 衛生・空調 | 日産設備工業 |
| 舞台 | 森平舞台機構 |
| 敷地面積 | 10,200平方メートル |
| 建築面積 | 856平方メートル |
| 延面積 | 781平方メートル |
| 階数 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 外部仕上 | |
| 屋根 | 本瓦葺き |
| 外壁 | 色モルタル下地しっくい塗 |
| 施工期間 | 1990年12月~1992年3月 |
| 総工事費 | 436百万円 |
受賞データ
| 1993年 | いらか賞 |
| 1994年 | 林野庁長官賞、くまもと景観賞 |
| 1995年 | 照明普及賞(優秀照明施設賞) |
| 1998年 | 公共建設賞特別賞 |
建築家プロフィール

| 石井 和紘(いしい かずひろ) | |
| 1944年 | 東京都生まれ |
| 1967年 | 東京大学卒業 |
| 1974年 | イェール大学修士号取得 |
| 1975年 | 東京大学大学院博士課程修了、石井和紘建築研究所設立 UCLA、日本大学、イェール大学、講師をつとめる。 |
| 現在 | 大阪大学、早稲田大学、東京大学で講師をつとめる。 |
| 主な作品 直島文教地区、54の窓、数寄屋邑(建築学会賞)、直島町役場、北九州市立国際交流会館、国立市立郷土会館、岡山県立ヨットクラブハウス、宮城県立支倉常長サン=ファン=バウティスクドック博物館および関連施設 |
|
| 受賞歴 | |
| 1990年 | 日本建築学会賞 |

